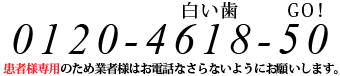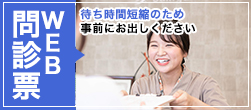小児矯正はいつから始める?年齢別の適切なタイミングと治療の流れを徹底解説
こんにちは。大阪府摂津市、大阪モノレール「南摂津駅」より徒歩3分にある千里丘・鳥飼からもアクセス良好な歯医者「さきがけ歯科クリニック摂津本院」です。

「いつから小児矯正を始めるべきか」と悩んでいる保護者の方は多いのではないでしょうか。
成長期の歯並びの問題を放置すると、大人になってからの矯正が難しくなったり、健康面や見た目にも影響が及んだりすることがあります。
この記事では、小児矯正はいつから始めるとよいか解説します。大人の矯正との違いや治療法、費用などについても解説しますので、お子さまの矯正治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
小児矯正とは

小児矯正は、成長期の子どものあごの発育を利用して、歯並びや噛み合わせの改善を目指す治療方法です。
子どもはあごの骨がまだ柔らかく、成長の途中にあるため、歯やあごの位置をコントロールしやすいという特徴があります。取り外し可能な装置や固定式の装置を使い、あごの成長をコントロールしながら進められます。
矯正の開始時期や治療内容は、歯の生え変わりや成長の進み具合によって異なるため、定期的な歯科受診が重要です。
大人の矯正との違い
小児矯正と大人の矯正の大きな違いは、あごの成長を利用できるかどうかでしょう。大人の場合、あごの骨の成長が完了しているため、骨格の調整は難しいです。そのため、大人の矯正では、主に歯を移動させて歯並びを改善していきます。
一方、小児矯正では、あごの成長を利用できます。身体が成長途中なので、顎の骨の成長をコントロールしてバランスを整えることが可能なのです。これにより、将来的な歯並びや噛み合わせのトラブルを予防することができます。
小児矯正はいつから始めるべきか

小児矯正は一般的に6〜10歳ごろの、乳歯と永久歯が混在する混合歯列期に行われます。この時期であれば顎の成長を利用して治療を進めることができます。
ただし、症状や個人差によって治療を開始する時期は異なります。
乳歯列期・混合歯列期・永久歯列期の違い
乳歯列期はすべて乳歯の時期、混合歯列期は乳歯と永久歯が混在する時期、永久歯列期はすべて永久歯が生えそろった時期を指します。混合歯列期は顎の成長や歯の移動がしやすく、矯正治療の効果が期待できます。
一方で、永久歯列期は成長が落ち着くため、治療の選択肢が限られる場合があるのです。
早すぎる・遅すぎる開始のリスク
矯正治療を早く始めすぎると、成長に合わせて再治療が必要になる場合があります。
一方、顎の成長が終わってから治療を開始すると、抜歯や外科的処置が必要になる可能性があります。適切な時期を見極めるためには、定期的に歯科医院を受診して、歯科医師に相談することが大切です。
小児矯正が必要となる主な症状とサイン

小児矯正が必要となる主な症状やサインについて解説します。
歯並びや噛み合わせのチェックポイント
お子さまの歯並びや噛み合わせを日常的に観察することで、異常などの早期発見につながります。例えば、前歯や奥歯がきちんと噛み合っていない、歯が重なって生えている、前歯が出ている、受け口になっているなどの様子が見られる場合は注意が必要です。
また、いつも口が開いている、食事の際に噛みにくそうにしているといった行動も、噛み合わせの問題を示している可能性があります。
受け口・出っ歯・すきっ歯などの症状
下の歯が前に出ている受け口、上の歯が前に出ている出っ歯、歯と歯の間に隙間があるすきっ歯などは、矯正治療の対象となる症状です。見た目だけでなく発音や咀嚼、将来的な歯の健康にも影響を及ぼすことがあるため、早めに歯科医師に相談しましょう。
こんな場合は早めに相談を
歯並びや噛み合わせ以外にも、指しゃぶりや口呼吸が長く続いている、顎の左右差が目立つといった場合は、歯科医師に相談しましょう。
また、乳歯の早期脱落や永久歯の生え変わりが遅いといった場合も、歯並びや噛み合わせに影響を及ぼす可能性があるため、早期に相談することが望ましいです。
小児矯正の治療方法と流れ

小児矯正の治療方法と流れについてご紹介します。
第1期治療と第2期治療
小児矯正には大きく分けて、第1期治療と第2期治療があります。第1期治療は主に6~12歳頃の混合歯列期に行われ、顎の成長を利用して歯並びや噛み合わせの土台を整えることを目的とした治療が行われます。
これに対して第2期治療は、永久歯が生え揃った中学生以降に行う治療です。矯正装置を使用して歯を細かく動かし、歯並びや噛み合わせを調整します。
小児矯正で使用される主な矯正装置
小児矯正で使用される装置には、取り外し可能な床矯正装置やマウスピース型の矯正装置、固定式の急速拡大装置などがあります。
床矯正装置は成長期の顎の幅を広げる目的で使用されます。口呼吸や舌癖などを改善し、顎が正しく成長するように促すマウスピース型の装置が使用されるケースもあります。いずれも、お子さんへの負担が少ないのが特徴です。
固定式の装置は、より確実に顎の位置をコントロールしたい場合に選択されることがあります。使用する装置は、お子さんの歯並びの状態や生活習慣に合わせて選択されます。
治療の一般的な流れ
小児矯正の一般的な流れは、まず初診でのカウンセリングや検査から始まります。その後、治療計画の説明を受け、ご家族の同意のもと治療が開始されます。
定期的な通院で装置の調整や経過観察を行い、必要に応じて治療内容の見直しが行われます。治療期間や通院頻度には個人差があり、装置の使用状況や日常の習慣によって異なります。
小児矯正のメリットとデメリット

小児矯正を検討する際にはメリットやデメリットについて理解しておくことが大切です。
小児矯正のメリット
小児矯正では、顎の成長を利用しながら歯並びや噛み合わせが自然に整うように促します。特に、成長期の子どもの骨は柔らかいため、歯や顎の位置を整えやすいとされています。これにより、将来的に抜歯や外科的な処置が必要になるリスクを減らせる可能性があります。
また、発音や咀嚼機能、見た目の改善など、心身の発達に良い影響を与えることも期待されています。
小児矯正のデメリットや注意点
一方で、成長過程にある子どもの歯や顎の状態は変化しやすいため、治療期間が長くなる場合があります。永久歯が生えそろったあとに、再度矯正治療が必要になるケースもあるでしょう。
また、治療には定期的な通院や装置の管理が必要で、本人やご家族の協力が欠かせません
小児矯正の費用と治療期間の目安
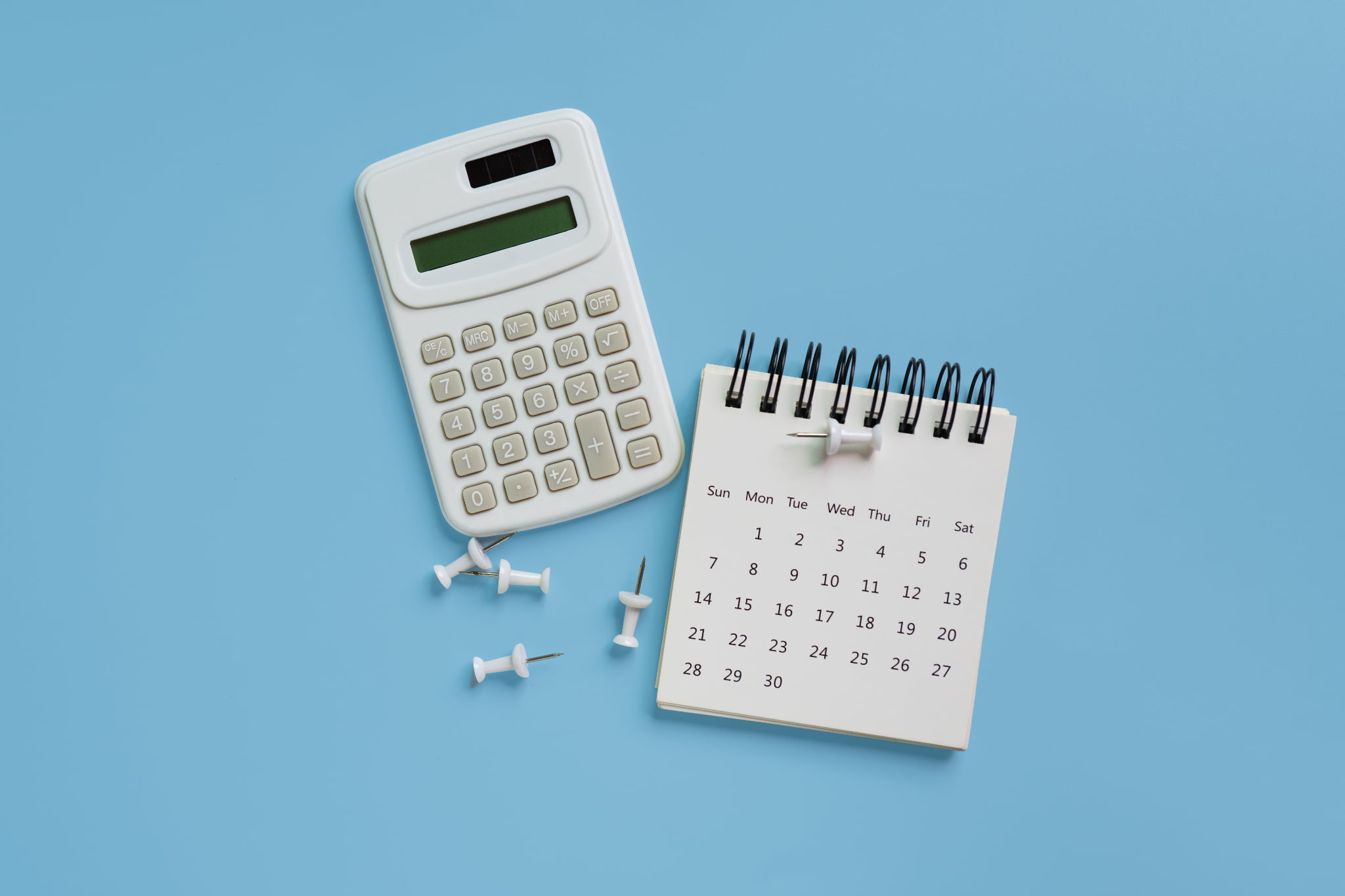
小児矯正を検討する際に気になる費用や治療期間について解説します。
治療費の相場と内訳
小児矯正の費用は、30万〜50万円が相場です。治療の内容や治療を受ける地域、使用する装置によって変動します。また、上記とは別に、初期相談料や検査・診断料、定期的な調整料などがかかる場合もあります。
治療期間の目安と通院頻度
治療期間は、歯や顎の成長段階や症状の程度によって異なります。一般的には1年から3年ほど必要な症例が多いでしょう。治療は顎の成長に合わせて進めるため、経過観察を含めて長期にわたる場合もあります。
通院頻度は、装置の調整や経過観察のために1〜2か月に1回程度が一般的です。治療の進行状況によっては、さらに間隔をあけて通院することもあります。
小児矯正を始める際のポイントと家庭でできるサポート

矯正治療の効果を高めるためには、家庭でのケアが欠かせません。毎日の歯みがきを丁寧に行い、虫歯や歯肉炎を予防しましょう。よく噛んで食べられるように、食材やメニューも意識してみてください。
指しゃぶりや爪かみなどの癖がある場合は、歯並びに影響を与えることがあるため、少しずつ改善を目指すことが望ましいです。
日常生活のなかで無理なく続けられる工夫を取り入れ、子どもと一緒に治療に前向きに取り組むことが大切です。
まとめ

小児矯正は、子どものあごの成長を利用して、歯並びや噛み合わせが整うように促す治療です。始める時期は症状や成長のスピードによって異なります。一般的には6〜10歳ごろが目安とされていますが、個人差があるため歯科医師に相談することが重要です。
小児矯正を検討されている方は、大阪府摂津市、大阪モノレール「南摂津駅」より徒歩3分にある千里丘・鳥飼からもアクセス良好な歯医者「さきがけ歯科クリニック摂津本院」にお気軽にご相談ください。
当院は、虫歯・歯周病治療、小児歯科だけでなく、インプラント治療や矯正治療、予防歯科などにも力を入れています。恐怖症や嘔吐反射で歯科治療を受けられない方のために、静脈内鎮静法も対応しております。
当院のホームページはこちら、初診のWEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。